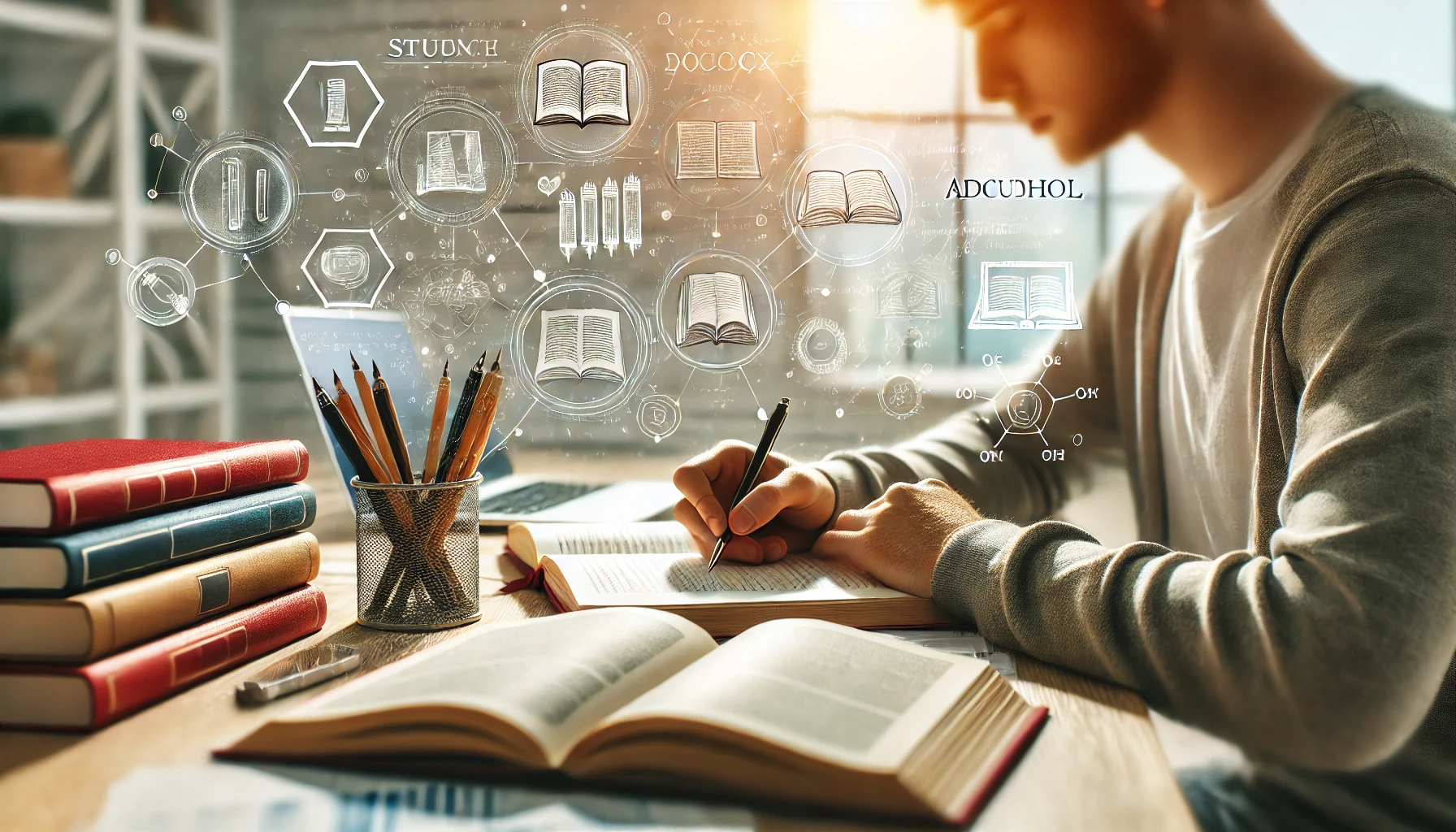第1章 はじめに:論述が苦手な人の共通点とこの記事で得られること
「論述」と聞くと、堅苦しくて難しい印象を持つ方も多いのではないでしょうか。実際、高校や大学での課題、小論文試験、資格試験などで「何を書けばいいのかわからない」と悩む声はよく聞かれます。共通しているのは、「構成のイメージが持てない」「根拠がうまく出せない」「書きながら迷子になる」という3つのつまずきです。
論述はセンスや特別な才能が必要なわけではありません。必要なのは「型」を理解し、その中で自分の考えを整理する練習です。本記事では、論述の基本構成、失敗しやすいポイント、説得力を高めるテクニック、そして日常での練習方法までを網羅します。
さらに、具体例や悪い例の改善、実際の論述例文も掲載。表形式でメリット・デメリットを整理し、初めての方でも安心して取り組める内容にしています。
| 読むメリット | 詳細 |
|---|---|
| 基本の型がわかる | 序論・本論・結論の流れをマスター |
| 説得力が上がる | 根拠の出し方と表現の工夫を習得 |
| 試験対策になる | 高得点を取るための注意点を解説 |
この記事を読み終えるころには、「どう書けばいいか分からない」から「こう書けば伝わる!」へと変わっているはずです。
第2章 論述とは何か?なぜ重要なのかを理解しよう
論述とは、自分の考えや意見を筋道立てて説明し、読み手を納得させる文章形式です。感想や日記のように感情を中心に書くのではなく、「主張」「根拠」「結論」を明確に示すことが求められます。
現代社会では、論述力は試験だけでなく、仕事や日常生活でも役立ちます。プレゼン資料の作成、議論での発言、SNSでの情報発信など、あらゆる場面で「説得力ある文章力」が評価されます。
論述と感想文の違い
| 項目 | 論述 | 感想文 |
|---|---|---|
| 目的 | 読み手を納得させる | 自分の感情を伝える |
| 構成 | 主張・根拠・結論 | 体験・感情の描写 |
| 根拠 | 必須 | 必要ない場合も多い |
よくある勘違いは「たくさん書けばいい」というもの。字数を埋めることに集中すると、論理が飛躍しがちです。また、感想と論述を混同してしまい、根拠が弱い文章になることもあります。
ポイントは、事実やデータ、具体的な事例をもとに主張を支えること。感情だけでは説得力が不足しますが、事実と組み合わせれば強い論述になります。
第3章 論述文の基本構成をマスターする
論述の基本は「三段構成」です。これは古くから使われてきた型で、読み手に分かりやすく伝えるための黄金ルールです。
三段構成の概要
| 段階 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 序論 | テーマ提示・主張予告 | 読み手の関心を引く |
| 本論 | 根拠・具体例を展開 | 複数の視点から説明 |
| 結論 | 主張の再確認・締め | 読み手に印象を残す |
序論では、テーマと自分の立場を簡潔に示します。
本論では、複数の根拠を挙げ、事実や事例で支えます。根拠は2〜3個が理想。段落を分けて展開し、読みやすくします。
結論では、序論の主張を再度強調し、全体をまとめます。
悪い例は、序論が長すぎて本論に入る前に読み手が飽きてしまうケース。また、結論で新しい主張を出すのもNGです。序論・本論・結論の役割を意識し、全体のバランスを整えることが大切です。

第4章 初めて論述を書くときにやりがちな失敗と改善例
初めて論述を書くと、つい内容よりも「とにかく字数を埋める」ことに意識が向きがちです。その結果、主張がぼんやりしていたり、根拠が不足していたりと、説得力の弱い文章になってしまいます。
よくある失敗例は以下の通りです。
| 失敗例 | 問題点 | 改善例 |
|---|---|---|
| 主張が曖昧 | 立場がはっきりしない | 序論で立場を明言する |
| 根拠不足 | 意見だけで支える | データや事例を加える |
| 論理の飛躍 | 根拠と結論がつながらない | 根拠→理由→結論の順に書く |
| 反対意見無視 | 一方的で説得力が落ちる | 反対意見に触れて反論する |
例えば「部活動は重要だ」という主張だけでは弱く、「部活動は社会性を養い、協調性を高めるため重要だ」と根拠を加えることで説得力が増します。
また、反対意見に一言でも触れると文章に深みが出ます。「確かに勉強時間は減るが、それ以上に得られる経験は大きい」といった形です。
第5章 説得力を高める文章表現のテクニック
説得力を持たせるには、内容だけでなく表現方法にも工夫が必要です。
まずは具体性を高めましょう。「多くの人」と書くよりも「約7割の高校生」と数値を示す方が信頼性が上がります。
効果的な表現方法
- 接続詞を適切に使う(しかし、なぜなら、つまりなど)
- 指示語を正確に使い、曖昧さを避ける
- 強調したい部分は文の冒頭や末尾に配置する
- 一文を長くしすぎない(40文字以内を目安)
例えば、「私は運動部に入るべきだと思う。なぜなら〜」と理由を接続詞で自然につなげると、読み手が流れを追いやすくなります。
また、曖昧語(色々、たくさん)よりも「具体例」「数字」を優先的に使うことで、文章全体の説得力が底上げされます。
第6章 根拠の種類と使い分けを身につける
根拠は論述の土台です。種類ごとに使い分けることで、文章に厚みが出ます。
| 根拠の種類 | 特徴 | 使用例 |
|---|---|---|
| 統計データ・調査結果 | 客観性が高く信頼されやすい | 「文科省の調査によると…」 |
| 専門家の意見・研究結果 | 権威性が加わる | 「教育学者○○氏は…と述べている」 |
| 歴史的事実・過去事例 | 時間的裏付けがある | 「過去の○○事件では…」 |
| 身近な体験・観察 | 読者の共感を得やすい | 「私の学校では…」 |
例えば教育のテーマなら、統計データで現状を示し、専門家の意見で裏付け、最後に自分の体験を添えるとバランスの良い文章になります。
同じ根拠ばかりだと偏りが生じるため、2〜3種類を組み合わせるのが理想です。

第7章 悪い例と改善例で理解を深める
具体的な失敗例と改善例を比較すると、何が不足しているのかが明確になります。以下はよくあるパターンです。
| 悪い例 | 問題点 | 改善例 |
|---|---|---|
| 部活動は大切だと思う。楽しいからだ。 | 根拠が主観的で浅い | 部活動は協調性や忍耐力を養うため大切だ。例えば試合での役割分担や練習の継続は社会生活でも役立つ。 |
| スマホは便利だ。色々なことができるからだ。 | 「色々」が曖昧 | スマホはスケジュール管理や調べ物など、学習効率を向上させる機能が多く搭載されているため便利だ。 |
| 環境問題は深刻だ。だから解決すべきだ。 | 根拠不足で説得力が弱い | 環境問題は、温室効果ガスの増加により気温上昇や異常気象が増えるなど生活に影響を与えるため、早急な対策が必要だ。 |
改善例では、具体的な事実や例を加え、読者が「なるほど」と納得できる形に整えています。曖昧な言葉は避け、数値や事例で補強することがポイントです。
第8章 テーマ別の論述例文集
ここでは3つのテーマを例に、実際の論述例を示します。型と表現の参考にしてください。
例文1:部活動の意義について
序論:部活動は、生徒の社会性を育む重要な場である。
本論:協調性や責任感を養えるだけでなく、努力を継続する力も身につく。例えば試合や発表会に向けて役割を果たす経験は、将来の職場でも活かせる。
結論:このように、部活動は単なる趣味活動ではなく、人間形成に寄与する大切な教育の一環である。
例文2:デジタル教科書の導入について
序論:デジタル教科書は教育現場に大きな変化をもたらす。
本論:情報の更新が容易で、検索機能により効率的な学習が可能になる。また、音声や動画による学習支援で理解が深まる。一方、画面疲労や集中力低下といった課題もある。
結論:利便性と課題の両面を踏まえた活用が求められる。
例文3:テクノロジーと人間関係
序論:テクノロジーの進化は人間関係の形を変えている。
本論:SNSは遠くの人とつながる一方で、直接会う機会が減る傾向もある。バランスを取る工夫が必要だ。
結論:テクノロジーを適切に使い、人間関係を豊かに保つことが大切である。
第9章 5分でできる論述力トレーニング
短時間でも続けられる練習法を取り入れることで、無理なく論述力を鍛えられます。
トレーニング例
- 簡単なテーマを決め、序論→本論→結論を書き出す(3〜4文)
- 主張+根拠+結論を30文字以内でまとめる
- 書いた文章を次のチェックリストで自己採点する
論述チェックリスト
| チェック項目 | ○/× |
|---|---|
| 主張が明確か | |
| 根拠が複数あるか | |
| 論理が飛躍していないか | |
| 反対意見に触れているか | |
| 結論が序論と一致しているか |
例えば「朝ごはんは必要か」というテーマで、5分間で短く論述を書く習慣をつけると、本番でも迷わず構成を組めるようになります。継続が力になるため、毎日1テーマを目安に続けると効果的です。
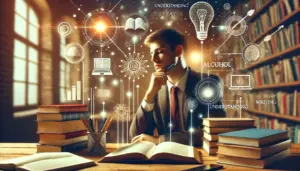
第10章 高得点を取るための実践対策
論述で高得点を取るためには、知識や練習だけでなく、試験本番での戦略も重要です。特に時間配分は成否を分けます。序論・本論・結論の配分をあらかじめ決めておきましょう。例えば50分なら、序論10分、本論30分、結論5分、見直し5分という流れが理想です。
よくある減点ポイントと回避法
| 減点ポイント | 回避法 |
|---|---|
| 主張が曖昧 | 序論で自分の立場を明言する |
| 根拠が不十分 | 各根拠に具体例を添える |
| 論理の飛躍 | 根拠→理由→結論の順に書く |
| 反対意見への配慮不足 | 反論を簡潔に加える |
試験直前には、過去問や模擬問題を使い、制限時間内で書く練習をしておくと安心です。また、書き終わったら必ず読み返し、誤字脱字や論理のつながりを確認しましょう。
第11章 論述力を伸ばす日常習慣と便利ツール
論述力は日々の生活の中で磨くことができます。ニュース記事を読んだら「自分は賛成か反対か」を考え、理由を2つ挙げる練習をしてみましょう。読書の際も、ただ内容を追うだけでなく、筆者の主張と根拠を意識します。
おすすめ日常習慣
- 社会問題について家族や友人と意見交換する
- 読書後に要約メモを作る
- 週1回は短い論述文を書きSNSやノートに記録する
便利ツール例
| ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| Google ドキュメント | 音声入力で素早く下書き可能 |
| Grammarly | 英語論述の文法チェック |
| 日本語校正サポート | 誤字脱字・表記ゆれを修正 |
| mindmeister | 論点整理に役立つマインドマップ作成 |
ツールを活用することで、効率よく質の高い文章を仕上げることができます。
第12章 まとめと次のステップ
この記事では、論述の基本構成、説得力を高めるテクニック、練習方法、試験対策、日常での鍛え方までを幅広く解説しました。ポイントは次の通りです。
重要ポイントまとめ
- 序論・本論・結論の三段構成を守る
- 根拠は複数の種類を組み合わせる
- 曖昧な表現を避け、具体的な事実や数値を盛り込む
- 反対意見に触れてバランスを取る
- 日々の習慣とツールで継続的に鍛える
次のステップとして、まずは身近なテーマで短い論述を書くことから始めましょう。続けることで、論理的思考力と表現力が自然と身につきます。学んだ型を使いこなし、自信を持って文章が書けるようになるはずです。