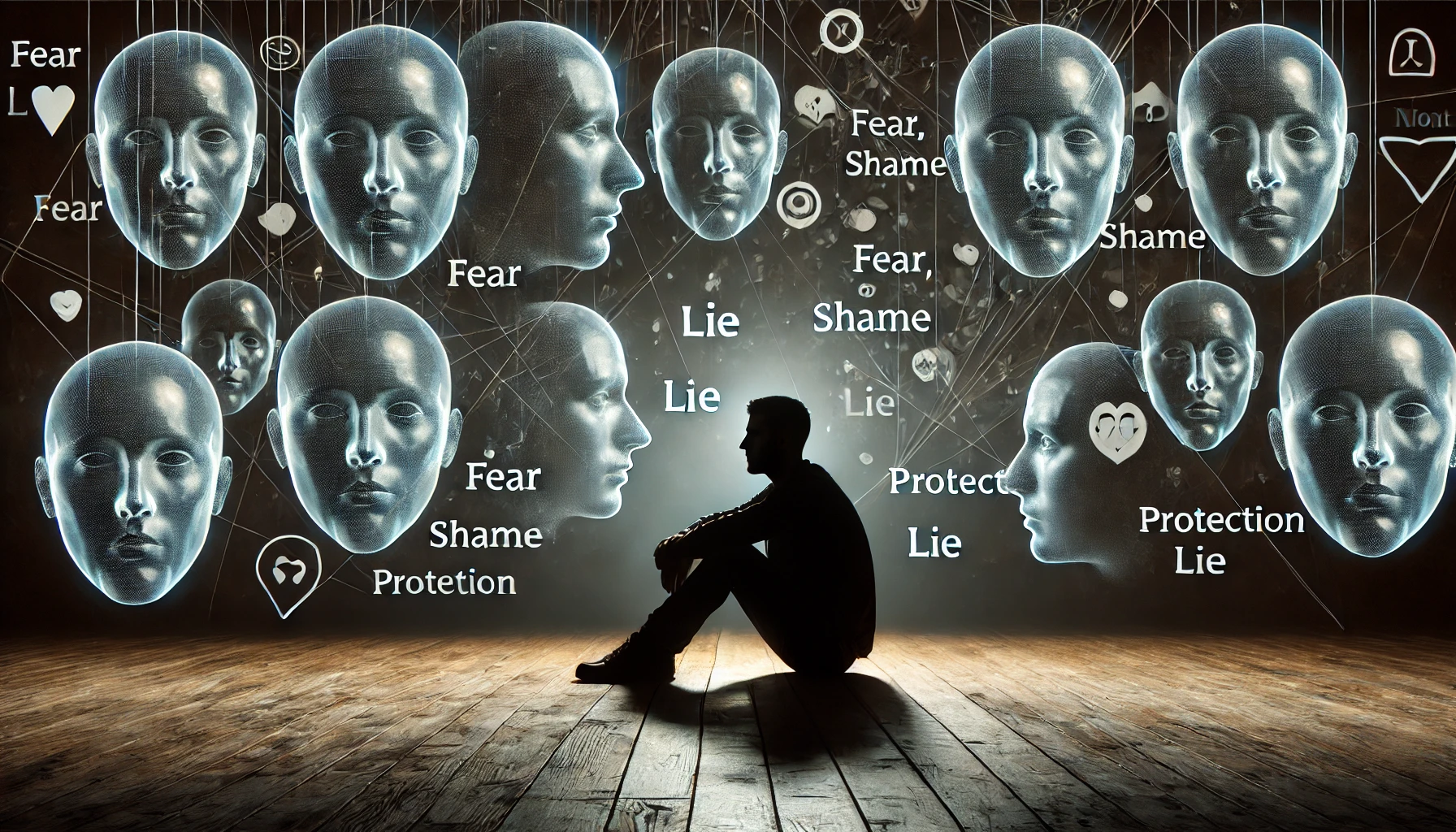はじめに──嘘をつく人の“裏側”には何があるのか?
誰しも一度は、「この人、なんでこんな平気で嘘をつくんだろう?」と疑問に感じたことがあるかもしれません。特に職場や家庭など、信頼関係が求められる場面での嘘は、相手への印象を大きく左右します。けれど、嘘をつく人をただ責める前に、その“背景”に目を向けてみたことはあるでしょうか?
嘘は決して突発的な行動だけではありません。実は、育った環境や家庭での関わり方、人との接し方によって、嘘を「必要なもの」として学習してしまったケースもあるのです。たとえば、子どものころに厳しい叱責を受けて育った人が、「本当のことを言うと怒られる」と思い込み、嘘を自衛手段として身につけたケースもあります。
本記事では、「嘘をつく人の心理」と「育ちの影響」に注目し、その原因や行動のしくみを丁寧に解説していきます。あわせて、周囲への影響や改善のステップ、自分や身近な人との向き合い方についても具体的に紹介します。
まずは、「嘘をつく人の特徴」から一緒に見ていきましょう。
嘘をつく人の特徴とは?表に出にくい行動パターンを探る
嘘をつく人には、いくつか共通する特徴がありますが、その多くは一見してわかりづらく、見抜くのが難しい場合もあります。以下のような行動パターンに心当たりはないでしょうか?
| 特徴 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自己保身が強い | 責任逃れのための言い訳が多い | 嘘と気づきにくい |
| 話を盛る癖がある | 自分を大きく見せる発言が多い | 信用しづらさにつながる |
| 言動に一貫性がない | 前に言ったことと違うことを言う | 無意識の嘘の可能性も |
このようなタイプの人は、深く追及されることを嫌う傾向もあります。話を濁したり、質問をすり替えたりする場面に遭遇したことがある方も多いのではないでしょうか。
また、嘘には「悪意のある嘘」だけでなく、「善意の嘘」「自己保身の嘘」も含まれます。すべての嘘が意図的とは限らないため、「なんでそんなこと言うの?」と感じたら、背景にある心理を探ってみることも大切です。
では、そもそも人はなぜ嘘をついてしまうのでしょうか?次の章ではその心理について掘り下げていきます。
なぜ人は嘘をつくのか──心理と本能に潜む本当の理由
人が嘘をつく理由には、さまざまな心理が関係しています。大きく分けると以下の3つに整理できます。
| 理由 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 自己防衛 | 自分を守るため | 怒られたくないから隠す |
| 欲求達成 | 得をしたい、評価されたい | 成績を盛って話す |
| 人間関係の維持 | 相手を傷つけたくない | お世辞、社交辞令 |
たとえば、「自分が悪く思われたくない」「本音を言ったら嫌われるかも」といった不安から、無意識に嘘をついてしまう人も多くいます。こうした嘘は、本人すら気づいていない場合もあり、繰り返すことで“癖”となって定着することも少なくありません。
特に、幼少期から「正直に話すと怒られる」という経験を繰り返してきた人は、嘘を“安全装置”として使うようになりやすい傾向があります。このように嘘は、防衛本能や心の傷から生まれるものでもあるのです。
次章では、こうした“嘘の芽”がどのようにして育ちのなかで形成されるのかを詳しく見ていきましょう。

嘘と育ちの関係──“どんな家庭で育ったか”が性格を作る
嘘をつく習慣は、生まれつきのものではなく、育った環境によって少しずつ形成されていくことが多いとされています。特に子ども時代の家庭環境は、その人の性格や対人スキルに大きな影響を与えます。以下は、嘘をつく傾向が強くなる可能性のある育ちの一例です。
| 育ちの傾向 | 内容 | 心理的影響 |
|---|---|---|
| 厳しい家庭 | 少しの失敗でも強く叱られる | 隠す=安全と学習する |
| 愛情不足 | 親からの関心が薄い | 嘘でも注目を得ようとする |
| モデルが嘘をつく | 親が日常的に嘘をつく | 嘘は当たり前という価値観に |
たとえば、親が「あとでね」と言って実現しないことを繰り返していると、子どもは「嘘をついてもいい」と無意識に学ぶことがあります。また、過度に期待されて育つと、プレッシャーに押されて「できているように装う」癖がつくこともあります。
嘘は突然芽生えるものではなく、日々の環境や言葉が少しずつ土台を作っていきます。親の言動や対応、兄弟関係、周囲の大人たちの振る舞い──それらが子どもにとって「正解のモデル」として定着してしまうのです。
続く章では、さらに成長過程で嘘がどう定着していくのかを探っていきましょう。
幼少期の嘘が性格に?成長過程での“刷り込み”に注目
小さな子どもが嘘をつく場面は、決して珍しくありません。たとえば「おもちゃ片付けたよ」と言っていなくても、本人は「片付けたことにしたい」という思いから嘘をつく場合があります。この段階では“現実と願望”の境界が曖昧であり、発達上自然な行動といえます。
ところが、これに対する大人の対応が、その子の後の嘘の傾向を左右することがあります。以下のような対応の違いによって、結果が大きく変わるのです。
| 大人の対応 | 子どもの反応 | 長期的影響 |
|---|---|---|
| 強く叱る | 怖くて隠す | 嘘が常態化 |
| 理由を聞く | 話せる環境になる | 正直に話す癖が育つ |
| 無関心 | 反応を求めて嘘を重ねる | 注目欲求としての嘘 |
思春期になると、親よりも友人との関係性が重視され始め、自分を良く見せたいという欲求が強くなります。その中で「つい見栄を張ってしまう」「嘘で繋ぎとめようとする」といった行動が定着しやすくなります。
つまり、幼少期からの積み重ねが、その人の「嘘との付き合い方」を形づくるのです。次章では、嘘の背後にある心の傷や不安について掘り下げていきます。
嘘をつく人の心の奥にある“不安と傷つきやすさ”
嘘をつく人の中には、一見すると堂々としていたり、社交的に見えたりするタイプもいます。しかしその内面には、「ありのままの自分を見せるのが怖い」という深い不安が潜んでいることも少なくありません。
たとえば、以下のような内面的背景が、嘘という行動に表れることがあります。
| 心の状態 | 嘘の内容 | 背景の感情 |
|---|---|---|
| 自信のなさ | 実力以上に話を盛る | 認められたい不安 |
| 否定への恐怖 | 本当の気持ちを隠す | 傷つくのが怖い |
| 孤独感 | 仲間外れを恐れて話を合わせる | 居場所を求めている |
実際に、30代女性Aさんは「昔から親に否定され続けて育ち、素直に話すと叱られることが多かった」と話します。その結果、社会に出ても本音を伝えるのが苦手で、気づくと“相手に合わせた嘘”を自然と口にしていたそうです。
このように、嘘はただの「悪意」ではなく、「自己防衛」「恐怖心の回避」からくる行動でもあります。相手をコントロールしようとしているわけではなく、自分を守る手段として身につけている人も多いのです。
続く章では、心理学の視点から「嘘=病気なのか?」というテーマを考えていきます。
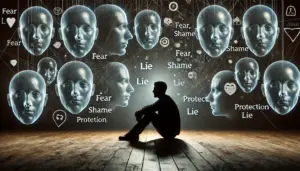
嘘をつくことは“病気”なの?性格なの?──心理学の視点から
「嘘をやめたいのに、つい口から出てしまう」と悩む人の中には、自分でもその原因がわからず苦しんでいるケースがあります。こうした慢性的な嘘癖には、心の病気や性格特性が関係していることも。ここでは心理学や精神医学の観点から、嘘との関係性を見ていきましょう。
| 観点 | 特徴 | 関連のある傾向 |
|---|---|---|
| パーソナリティ障害 | 自己愛・境界性・演技性など | 注目を集めるための嘘が多い |
| 発達特性 | ASDやADHDなど | 空気が読めず、意図せず嘘のように聞こえることも |
| 心因性の癖 | トラウマ・過去の否定経験 | 自分を守るために嘘が習慣に |
たとえば、自己愛性パーソナリティ障害の傾向がある人は、「周囲からよく見られたい」という気持ちが強く、話を大げさにしたり、事実をねじ曲げて話したりすることがあります。また、発達障害のある人は、“社交辞令”のようなあいまいな会話が苦手で、悪気なくズレた言動をとることも。
重要なのは、「嘘をつくこと」だけに注目するのではなく、その背後にある精神的な状態や性格傾向を正しく理解することです。必要であれば専門家のカウンセリングや診断を受けることも、自分を変える第一歩になります。
社会の中で嘘がもたらす影響──信頼、孤立、そして自己評価
嘘は一時的に問題を避けられるように見えても、長期的に見ると多くの人間関係に悪影響を及ぼします。特に日常的に嘘を繰り返す人は、信頼を失い、徐々に孤立していくリスクが高くなります。
| 影響 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|
| 人間関係の摩擦 | 話の食い違いが増える | 疑われることが多くなる |
| 信頼の喪失 | 小さな嘘でも積み重なる | 距離を置かれるように |
| 自己評価の低下 | 嘘でつながった関係に疲れる | 「自分はダメだ」と思いやすくなる |
たとえば、40代男性Bさんは「職場で評価されたい」という気持ちから、できていない仕事を“できた”と言って報告した結果、後でミスが発覚し、チームの信頼を大きく失ったそうです。その後は相談もされにくくなり、孤立感を深めてしまいました。
また、嘘を続けている本人も心のどこかで後ろめたさを感じています。「このままではダメだ」とわかっていても、どう改善すればいいのかわからず、ますます嘘に頼る…という悪循環に陥ることもあります。
では、嘘をつく人との関係はどう築いていけばよいのでしょうか?次章では、その対処法を紹介します。
嘘をつく人とどう付き合うか?信じたいけど、振り回されたくない人へ
身近に嘘を繰り返す人がいると、「信じたいけど、また裏切られるかも…」という葛藤を抱えることがあります。かといって完全に関係を切るのも難しい場合、どのように向き合えばいいのでしょうか。
| 対処法 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| 感情的に反応しない | 嘘を責めるより冷静に対応 | 相手が防衛的になりにくい |
| 境界線を持つ | 期待しすぎない・深入りしない | 自分の心を守れる |
| 行動で信頼を判断 | 言葉より実際の行動を見る | 誤解や思い込みを防げる |
実際に、30代女性Cさんは「恋人の嘘に振り回されて疲弊していた」といいますが、「毎回問い詰めるのをやめ、信頼できる部分だけで関わる」ようにしたことで、自分の心の安定を保てるようになったそうです。
相手を変えようとするよりも、自分の接し方を見直すことが、長続きする関係のヒントになることもあります。無理に信じる必要はありません。必要な距離を保つことで、冷静な目で関係を見直す余裕が生まれます。
次章では、「嘘をつく自分を変えたい」と思っている方に向けて、具体的な改善ステップを紹介していきます。

「育ち」を超えて変わりたい人へ──嘘をやめる3つのステップ
「もう嘘はやめたい」「正直に生きたい」と思いながらも、つい口から出てしまう——そんな悩みを抱える人は少なくありません。嘘が癖になってしまった背景には、育ちや環境、心の傷などがあることは前章までに紹介しましたが、自分を変えることは不可能ではありません。ここでは、嘘を手放していくための3つのステップをご紹介します。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 感情を言葉にしてみる | 怒りや不安も正直に口に出す練習 | 小さな本音から始める |
| 2. 自分の価値を再確認する | 嘘でごまかさなくてもいい自信を育てる | 自分を否定しない視点を持つ |
| 3. 「本当はどうしたい?」と問いかける | 嘘ではなく“本音”の選択肢を増やす | 習慣化が鍵になる |
たとえば、20代男性Dさんは「すぐ“平気だよ”と嘘をついてしまう」癖がありましたが、毎晩ノートに“本当はどう思っていたか”を書き出す習慣をつけたことで、少しずつ自分の感情に正直になれるようになったそうです。
大切なのは、完璧を目指さないこと。正直になるには練習が必要で、最初は失敗して当たり前です。まずは自分自身に対して“正直である”時間を増やすことが、他者との信頼関係の再構築にもつながっていきます。
次章では、実際に嘘を克服した人たちの体験談をご紹介します。
実録・変われた人の体験談──嘘をやめたきっかけは?
嘘をつく習慣を乗り越えた人たちは、どのような過程を経て変わっていったのでしょうか?ここでは5名の体験談をまとめました。それぞれの人生に寄り添いながら、改善のヒントを探ってみましょう。
| 名前(仮名) | 年齢・性別 | 変化のきっかけ |
|---|---|---|
| Aさん(28・女性) | 嘘で職場の人間関係が崩壊し、カウンセリングを受けたことで自分の「癖」に気づけた | |
| Bさん(35・男性) | 転職面接で嘘をつきすぎて落ち続け、等身大で話したときに初めて採用された経験が転機に | |
| Cさん(42・女性) | 子どもが自分の嘘を真似し始めてハッとした。以後「正直な姿勢」を家庭のルールに | |
| Dさん(31・男性) | 恋人に何度も嘘がバレて別れたあと、「本音で愛されたい」と自覚したことがきっかけ | |
| Eさん(24・女性) | 友人の指摘で「嘘をつかなくても受け入れてもらえる」と知り、少しずつ癖がなくなった |
多くの人が「誰かとの関係の中で気づいた」ことをきっかけに変化しています。嘘は一人で続けられるものではなく、周囲の反応や信頼があってこそ成立するものです。だからこそ、“他人とのつながり”が変化のきっかけになりやすいのです。
続く章では、読者からよく寄せられる「嘘」に関する悩みをQ&A形式でご紹介します。
よくある疑問Q&A:嘘をやめたい人が抱える悩みとは?
嘘にまつわる悩みは、人によってさまざまです。ここでは、特によく寄せられる5つの質問にお答えします。
Q1. 嘘をやめたいのに、やめられないのはなぜ?
→ 嘘が習慣化していたり、自分を守る手段として無意識に使っていることが多いためです。まずは「なぜ自分が嘘をついてしまうのか」を見つめることが第一歩です。
Q2. 嘘って病気なんですか?
→ 単なる性格の癖であることもありますが、パーソナリティ障害や発達特性が背景にある場合も。気になる方は専門機関への相談もおすすめです。
Q3. 子どもがすぐ嘘をつきます。どうしたらいい?
→ 怒るよりも「本当のことを話せたね、えらいね」と正直さを肯定する関わりが大切です。罰より信頼関係を意識しましょう。
Q4. 嘘をつかれた側としてはどう接すれば?
→ 嘘を暴いて責めるより、「正直に話しても大丈夫だよ」と伝える方が、相手の心を開かせやすいことがあります。境界線を持ちつつも、冷静に関わる姿勢がカギです。
Q5. 嘘をついてしまった過去をどう償えばいい?
→ まずは謝罪と再発防止の姿勢を言葉と行動で示すこと。すぐに信頼を取り戻すのは難しいですが、誠実さを積み重ねていくことで関係の修復は可能です。
次はいよいよまとめです。嘘の裏にある“育ち”や心の背景をふまえ、どんな視点で向き合えばよいのかを整理します。
まとめ──嘘の奥にある「育ち」に気づいたとき、本当の関係が始まる
嘘をつく人の行動には、単なる性格の問題ではなく、その人の「育ち」や「心の傷」が深く関わっていることがあります。親の期待や愛情不足、過去の否定経験、あるいは自分を守るための習慣として身についた嘘。それらは、本人すら気づかないうちに心の奥に根を張り、性格の一部のようになっていくのです。
しかし大切なのは、そうした背景に「気づくこと」。嘘を責めるだけではなく、「なぜその人は嘘を選ばざるを得なかったのか」という視点を持つことで、私たちはより深く人と関われるようになります。
| 視点 | 行動の変化 | 関係への影響 |
|---|---|---|
| 責めるより理解 | 相手の本音に目を向ける | 防衛反応が和らぐ |
| 境界線を大切に | 距離を保ちつつ関わる | 自分も疲弊しない |
| 正直を練習する | 小さな本音から始める | 信頼の再構築が可能に |
この記事を通して、「嘘=悪」と決めつけるのではなく、「その人がなぜそう振る舞うのか」に優しいまなざしを持てるようになっていたら、きっと人との関係はもっと柔らかく、あたたかなものになるはずです。
そしてもしあなた自身が「嘘をついてしまう」ことに悩んでいるなら、自分を責めるよりも、「変わりたい」と願うその気持ちこそが、変化の第一歩です。
本当の気持ちを言葉にできる日が、きっと来ます。焦らず、少しずつ。自分を理解することから始めてみましょう。